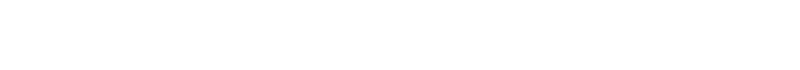ごあいさつ
理事長 佐々木 悦子
当研究所は、2013年4月に「公益財団法人」として新たにスタートしてから10年目となりました。この間の皆様からのご指導・ご助言や研究・研修委員の皆様のご活躍によって、「保険・医療・介護・福祉」に関する様々な調査研究活動、セミナー・研修会等の開催や、季刊誌「国民医療」の発行など充実が図られています。
今般の新型コロナウイルス感染拡大によって、日本の医療・介護提供体制や社会保障のぜい弱さが浮き彫りになりました。新興・再興感染症や災害など不測の事態においても、医療・社会保障充実のため当研究所の果たす役割は大きいと感じております。
引き続き、「保健・医療・介護・福祉」の向上と国民の保健衛生向上をめざし、調査・研究活動や情報発信の充実に努める所存です。今後とも、よろしくお願い致します。
医療・介護等の現場の改善に向けた調査・研究活動について
災害と地域医療
2025年、最初の『国民医療』の発行にあたり、みなさまにご挨拶を申し上げます。
旧年中は当研究所の活動に多大なるご尽力を賜り、誠にありがとうございました。
本年も保健・医療・介護・福祉の向上をめざして、調査・研究活動および情報発信の充実に努めます。引き続きご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
調査・研究活動について、「災害と地域医療の研究部会」を新たに設置しました。2024年度は災害を契機とした地域医療の再整備(再編統合など)の実態把握を進め、2025年度には実態把握をもとに、被災地の住民生活にもとづいた地域医療のあり方の模索を検討しています。
2024年12月には能登半島地震によって甚大な被害を受けた、奥能登地域(2市2町)において、公立病院へのヒアリング調査を実施しました。
奥能登地域では、市内・町内の一部の介護施設が震災によって使用できなくなるなどの被害を受けたことから、急きょ、公立病院内で閉鎖していた病棟を介護医療院として活用するなど、介護需要に対応されていることもわかりました。
奥能登の自治体は震災前の時点で、いずれも高齢化率がおよそ50%前後でした。直近の2025年2月12日に石川県が発表した(2024年10月1日時点での年齢別推計人口)データでは、2市2町の高齢化率は珠洲市54.1%、輪島市51.2%、能登町53.9%、穴水町51.8%と、すべての自治体で高齢化率が50%を超えています。
震災等によって人口減少が加速しており、医療・介護労働者数も減少しています。人口減少・高齢社会・担い手不足といった課題は、他の地域にも共通する内容です。地域の医療・介護体制の整備は人々が住み続けるために必要です。また、地域の重要な産業および経済の拠点としての医療・介護・社会福祉等の整備が重要と考えています。
軍事と医療の再整備
東日本大地震の被災地域では、「創造的復興」と称する惨事便乗型の構造改革が展開されたのは記憶に新しいところです。被災した人々の生活保障や、地域の医療・介護保障体制の整備が後景におかれました。
直近の能登半島地震の被災地においては、従来の惨事便乗型構造改革の展開に加えて、能登空港を重要な軍事拠点の1つとする整備事業が開始しています。
2024年4月1日には、政府が防衛力強化の一環として、能登空港を有事に備えて平時から自衛隊や海上保安庁が円滑に利用できるよう整備する「特定利用空港・港湾」の1つとして選定しました(能登空港を管理する石川県の同意があったため)。有事に備えて自衛隊の部隊の新たな配置、国民保護活動の拠点として2024年度から整備されることとなりました。
空港隣接地には、能登半島の公立4病院を再編統合した医療機関を新設する計画がすでに浮上しており、防衛力強化を盾に、軍事と医療の再整備計画という構想が明らかとなっています。一方で、被災した人々には2次避難を勧奨しておきながら、後日には退去期限を区切って移住を迫るなど、看過できない行政の姿勢が明らかとなっています。今後は、能登空港隣接地に集住移転を勧奨していくのではないかとの予測が成り立ちます。
被災地における軍事と医療の一体的整備についても注視したいと考えています。
コロナ禍での「留め置き死」を契機に調査研究に取り組む
調査研究活動の一環として、福祉国家構想研究会(事務局:京都府保険医協会)と合同で、新型コロナウイルス感染症に関する調査研究に取り組むことになりました。
具体的には、新型コロナウイルス感染症に罹患したものの、医療機関での治療を受けることができずに施設や自宅等に留め置かれて亡くなられた方々、いわゆる「留め置き死」に関する調査研究です。
どのような経緯で施設や自宅等に留め置かれてしまったのか、高齢者福祉施設や障害者福祉施設の利用者の方々が医療にかかることができず亡くなられたのはなぜか。ご遺族の方々の思いを受け止めるかたちで、調査研究体制を整備することとなりました。
47都道府県、保健所、医療機関、高齢者福祉施設、障害者福祉施設を対象に量的調査に取り組むとともに、ご遺族の方々にもご協力頂きインタビュー調査を予定しています。
「留め置き死」が起きる背景には、長年にわたる公的医療費抑制策の展開等により、常態化している人員不足、医療供給体制の再編・統合による医療機関数の減少と医療アクセス問題の深刻化、医師の絶対数の不足、病床数の削減、保健所の再編・統合などの影響があると考えています。
高齢者や障害者福祉施設、保健所や医療機関など、コロナ禍においても現場職員の方々の奮闘に依存していたにもかかわらず、現場に責任を転嫁するような言説が生まれる構造を変えていく必要があります。そもそも、構造的に「留め置き死」が起きる状態になっていたのではないかと推察し、調査による検証作業を進めているところです。